Morning glow
⑦
――テレポートを試みた僕とナナシは、目まぐるしく移り変わっていく景色に包まれていた。やがて浮遊感を失った足に地面を踏みしめる感触が訪れると同時に、一面まっさらだった視界が開けてくる。
一瞬の眩しさを払うように瞬きをすれば、そこには先程の道路とは全く異なる景色が広がっていた。
周囲には家のような建物が点在していて、どれも屋根から延びている棒の頂点に赤いリボンが結びつけられているといった風変わりなものだ。
奥の岩壁には小さな崖が幾つも突き出していて、いずれも昇れるように梯子が掛けてある。更には大きめの横穴も確認できた。
そして、この奇妙な空間を包み込むように岩山が囲っている景色は――正しく"谷間"と呼ぶに相応しい場所だった。
僕はテレポートが成功したことを再確認するように一歩、また一歩と歩み始める。しかし突然――右手が後方に引っ張られたことで動きが止まった。
即座に振り向けば、すぐ後ろにいたナナシと顔をぶつけそうになる。一方彼女の瞳はどこか虚ろで、目の前の僕ではなく周囲に広がる景色に向けられていた。
恐らく、脳内で今の状況を必死に整理しているんだろう。彼女にとってテレポートは初めての経験だから、無理もない。
数秒の沈黙の後。ナナシは我に返った様子で身動ぐと、ようやく僕と目を合わせてくれた。小さく開かれた唇から漏れた声は、微かに震えている。
「えっと……テレポートできたってこと……でいいんだよね?」
「うん、無事に目的地に移動できたよ。どうだった? 初めてのテレポートは」
「どう、って聞かれると……一瞬過ぎて何て言ったらいいか。それに、まだ足元がふわふわしてる感じ……」
彼女は戸惑いながらそっと自分の足元を見下ろす。その言葉通りふらつきを残していて、少し頼りなさげだ。
そういえばここに着いてからというもの、何故か右手だけが熱を帯びている。そっと下ろした視線の先にあったのは、固く結ばれたままの僕達の手。
そうだ――テレポートをしている間、お互いを離さないように手を掴んでいたんだった。ナナシも僕の様子に気付いたようで、繋がれた手に視線を向けると途端に目を丸くする。
「わっ、なんかごめん……!」
「ううん、私こそ気付かなくて」
僕は慌てふためきながら、ぱっと手を離した。宿っていた熱が引いていく感覚に切なさを覚えつつ、改めて懐かしの景色を眺める。
この谷の名は"サターンバレー"。険しい山や川といった自然の障壁の奥深くにあり、正に"地図にない場所"。
そして六年前の冒険の終着点ともいえる――僕にとって特別な地。見渡す限りでは特に大きな変化は感じられず、人が介入した痕跡というものも見受けられない。
あの頃と同じく、奇妙かつ馴染み深い空間が広がっているだけだ。
「変わった建物……誰かの家、なのかな?」
一方ナナシは側にあった建物にゆっくりと近付き、しげしげと眺めていた。そういえば先程から、この谷にいるはずの"住人達"の姿を見かけない。
まさかまた、事件に巻き込まれてしまったのか。嫌な可能性が浮かんできた時――ナナシの背後にあった茂みが揺れ動き、彼女の肩が面白いぐらいに跳ね上がる。
もしかしたらそこにいるのは。何者かなんとなく予想がついた僕は、自然と頬が緩んでいた。
「な、何っ? 何……!?」
「大丈夫だよ、ナナシ。そこにいるのはきっと、僕の"恩人"だから」
困惑するまま僕に振り向いたナナシは、要領を得ないといった顔をしている。すると突然、肌色の丸い突起物が飛び出したと思うと、もぞもぞと草をかき分けながら出てきた。
僕達の前に現れたのは、全身肌色の一頭身。体の半分ほどもある大きさの鼻と、頭の真っ赤なリボンが目を引く不思議な生物。
「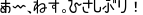 」
」
「やあ。六年ぶりだね、どせいさん!」
僕の元にひょこひょこと近付いてきたその生物は"どせいさん"という種族で、このサターンバレーの住人。
六年前の冒険の途中、ギーグの手下であるゲップーの一件で出会ったことで親しくなったんだ。
そして高度な技術力を以て、ギーグのいた"過去の最低国"へ赴く僕達を支援してくれたりと、感謝してもしきれないぐらい冒険を支えてくれた人々。
「 」
」
「僕こそ、こうして再会できて嬉しいよ」
彼ら特有の不規則なイントネーションが耳に馴染んでいく。六年経った今も、僕の姿を見てすぐに"ネス"だと気付いてくれたことが嬉しかった。
挨拶もそこそこに微笑むと、隣のナナシの様子をちらりと伺う。彼女にとっては未知の生物と出会うという一大イベント。
一体どのような反応を示すのか、この旅の中で非常に気にかかっていた部分でもある。
肝心の本人はというと、真顔のまま目の前の"どせいさん"を静かに見つめていた。あれ、好奇心旺盛なナナシだったら驚いたりといったリアクションを見せてくると思ったんだけど。
もしかして、彼女にとっては受け入れがたいことなんだろうか。段々と不安になってきて、どう声を掛けようかと脳内で言葉を捏ねていた時だった――。
「……かっわいい~!!」
ナナシは突然叫んだかと思うと、どせいさんの元に駆け寄っていった。彼の等身に合わせてしゃがみこむと、満面の笑みを向ける。
この反応を見るに、どうやら彼女のストライクゾーンに見事ヒットしたらしい。
「初めまして、私の名前はナナシっていいます。よろしくね! 前にネスから話は聞いていたけど、本当にかわいいなあ……!」
「 」
」
彼女の勢いに押されているのか、それとも照れているのか。表情というものがないから分かりにくいけど、彼もナナシを受け入れてくれたらしい。
気付けば僕達を囲むように、他のどせいさん達もその姿を現していた。みんな背中に袋を付けていて、それぞれはち切れんばかりに膨らんでいる。
「 」
」
「 」
」
「 」
」
次々とどせいさんが集まってくる光景にナナシは目を輝かせつつ、その口を鯉のように開閉させていた。
ここまで感激してくれるとは思っていなくて、僕の不安は杞憂に終わったことにひと安心する。
どせいさん達は僕らにコーヒーを振る舞ってくれるらしく、お言葉に甘えてナナシと一緒に椅子代わりの岩場に腰掛けた。
出されたコーヒーはこの谷ならではの独特の風味があり、あの頃と変わらない味で疲れを癒してくれる。
六年ぶりの再会で積もる話もあった僕は、どせいさん達と存分に語り合った。ナナシも彼等とすぐに打ち解けて、楽しそうに会話を交わしていく――。
***
大自然の中でコーヒー・ブレイクに心を満たされた後は、この付近にある"ぼくのばしょ"に向かうことにした。
そこはサターンバレーにある横穴からでないと入ることができない秘境の奥にある場所。名残惜しくもどせいさん達に別れを告げ、洞窟の中を進んでいった。
「はあ、もうちょっと居たかったなあ……」
「気持ちは分かるけど、これ以上は時間が厳しいよ。それに戻りもサターンバレーを通るんだから、またどせいさん達に会えるって」
何度も振り返りながら歩くナナシに、苦笑いを浮かべながらも宥める。この谷に来た目的はどせいさん達に会うためだけじゃない。
久しぶりにテレポートを使ってまで連れて行きたかった場所が、この先にあるんだ。洞窟を抜けると、相変わらず岩壁に挟み込まれた景色が広がる。
道自体は平坦だし、かつてのような危険な生物も見かけない。この分なら戻る際の体力は温存できるだろう。
陽光を受けて眩しそうに顔をしかめていたナナシも、次第に前を向いて歩き始めた。
「ここまで結構歩いてきたけど……この先にある"ネスのばしょ"ってどんなところだっけ?」
「まだ詳しく言ってなかったね。もうすぐ着くから、それまでのお楽しみってことで」
人差し指を立てながらウインクをしてみせると、ナナシの瞳に期待を表す光が宿った。足取りが軽くなった彼女を先導するように、僕も歩幅が大きくなったのを感じながら歩みを進めていく――。
やがて奥地へ進んでいく内、口数も少なくなってきた頃。何気なくナナシの様子を伺うと、その横顔には憂いに似たものが滲んでいた。
一体どうしたんだろう。流石に疲れてきたんだろうか。一旦休憩しようかと口を開く寸前、彼女は何かに気付いた様子で声を上げた。
「また洞窟が見えてきたよ。もしかして、あの中に"ネスのばしょ"があるってこと?」
「えっ、うん。あの洞窟の先にあるのが"ミルキーウェル"。その名の由来は実際に見てもらえれば分かるよ」
「名前だけは前にも聞いてたけど、一体どんな場所なんだろ……楽しみ!」
再び好奇心を呼び起こされたのか、ナナシからは先程のような曇りがかった面持ちは消え失せていた。
もしかするとあの表情は、変わり映えのない景色に思うところがあったからかもしれない。今はそうとしか考えられない。そうであってほしい。
胸の奥に引っかかるものを誤魔化すようにリュックを背負いなおすと、僕達は暗闇へと足を踏み込んでいった――。
この洞窟の構造はこれまでに訪れた場所に比べると至って単純で、絶壁を伝うように一本道を辿っていけばすぐに出口を見つけられる。
六年前に初めてここに入った時は、モンスターと化した植物やパワースポットの力を得て巨大化した"長年樹の芽"が行く手を阻んできた。
だけどこの頃にはポーラもジェフも能力を高めて更に頼もしくなっていたし、三人で力を合わせてなんとか突破できたんだ。
こうして苦難の末にたどり着いた秘境の奥底で、僕は突然幼い頃の記憶を呼び起こされた。
そして今も――ほんのりと甘い香りを漂わせる"白い泉"は、昔と変わりなく汚れない輝きを湛えていた。
どこか切なくも懐かしさを誘う光景に意識を奪われていると、隣にいたナナシから溜め息にも似た感嘆の声が上がる。
「噴水みたいに湧き出てる真っ白な水と、飛沫で辺りが靄がかってて……とっても綺麗」
「気に入ってもらえたなら良かったよ。まさにこの白い湧水こそが"ミルキーウェル"という名前の由来なんだ」
僕の言葉に頷きながらも、ナナシはこの神秘的な風景にすっかり魅了されていた。その頬は興奮からか赤く染まっていて、目を細めている姿はまるで幼子みたいに無邪気で。
そんな横顔に、つい見惚れてしまう。今この景色に包まれているナナシは何を想っているんだろう。
かつての僕と同じように、唯一無二の景色を心に刻みつけてくれたなら嬉しい――なんて考えていると、不意にナナシがこちらを振り向いた。
その瞬間、心臓が痛いほど大きく跳ね上がる。視線に気付かれたんだろうか。思わず硬直してしまった僕を気にする素振りもなく、彼女はゆっくりと口を開いた。
「実は……今朝から考えてたことがあって。ネスはこうして次々と素敵な場所に連れて行ってくれたり、ピンチになったら助けてくれるのに……対する私は無力で、一体何が出来てるんだろうって」
ナナシから紡がれたのは、予想もしていなかった言葉。僕にとって、それはあまりにも唐突な問い掛けだった。
そもそも見返りとか、そういったものを望んでナナシを"冒険"に誘ったわけではない。僕の力で君の長年の願いを叶えられるなら、と思って始めた旅だ。
「私、何となくわかってたんだ。リリパットステップで襲ってきたあの熊も、本当は弱そうな私を狙ってたんだろうなって……」
ナナシは俯きがちに呟くと、その拳をきつく握りしめていた。やっぱり、洞窟に入る前に彼女が見せていたものは――僕の思い過ごしじゃなかったらしい。
言いようもない焦燥に駆られた僕は、何度も首を横に振っていた。
「急に何言い出すんだよ。僕はナナシと一緒に自分の"旅の足跡"を辿りたい。君は昔から僕の"冒険"を追体験したがっていた。こうして今、お互いに満たされてるならそれでいいじゃないか」
「ネス……本当にありがとう。私、自分に何ができるのか……まだ分からない。だけど、この旅で少しでも"強く"なれる切っ掛けを見つけたい」
顔を上げたナナシの瞳には炎のような煌きが宿っていた。その視線に射抜かれた僕は返す言葉を失ってしまう。
彼女は幼馴染の僕ですら悟ることの出来ない水面下で、どこまでも自分の心と向き合おうとしていたんだ。
振り返ってみれば、ナナシは幼い頃から自身が抱えている暗部や激情といったものを曝け出してくれることは殆どなかったな。
先月この旅を始める切っ掛けになった日だって、彼女があれ程の願望を示してきたこと自体珍しいものだったんだ。
「突然こんなこと言ってごめん。どうしても私の本音、聞いて欲しくて」
いつも朗らかで、僕や周囲の人間を気遣ってくれて、前向きな姿勢を崩さない。それがナナシだった。
だけど今、彼女はこうして僕に胸の内に潜む弱みを曝け出してくれている。全て聞き入れた人間として、僕はそれに応えるべきなんだと思う。
「いいんだよ。僕こそ、ナナシが思いを打ち明けてくれて嬉しかったんだ。この旅、絶対に最後までやりきろう」
ナナシは抱えていた気鬱を吹き飛ばすような笑みを浮かべると、力強く僕の手を握ってくれた。その温もりに呼応するように、僕の心臓は激しく脈を打ち始める。
手を通じてお互いの体温が混ざり合うような感覚に浸る中、僕らは白乳色の霧の中で見つめ合っていた――。
どせいさんフォントは未対応の方もいらっしゃるので、どせいさんの台詞だけ画像にしてあります。
折角のどせいさん登場回なので少しだけ凝ってみました。
続き
戻る